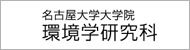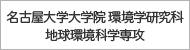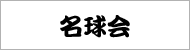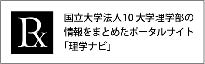新着情報
「地球環境科学と私」第五十二回
2025.3.11
「地球環境科学と私」第五十二回は地球史学講座 垣内田 滉さんによる 拡げる、触れる、考える です.
拡げる、触れる、考える 地球史学講座 垣内田 滉
河川水や海水中の無機溶存炭素の炭素同位体比は水中の生物の活動、海洋循環を調べる上で有効なツールです。しかし、天然水試料は採取から測定までに時間がかかることが多く、その間に微生物によって同位体比が変化してしまいます。そこで、私は卒業研究において、この変化を抑え、高精度炭素同位体分析を可能にする水試料の保存方法を検討しました。具体的には、一般に用いられる塩化水銀の代わりに塩化ベンザルコニウムを使用する方法を試み、塩濃度や懸濁物質など、どのような水試料の条件が殺菌剤の効果を低下させるかを詳細に検討しました。
修士研究では水中考古学的な研究にも取り組み始めました。水中考古学は、海や湖に沈んだ遺跡を対象にする考古学の一分野です。日本の専門家は少なく、国内には十分調査されていない水中遺跡が多く存在すると考えられています。そのような中で、長崎県の鷹島水中遺跡は調査が進んでいる遺跡の一つです。鷹島水中遺跡からは、鎌倉時代の弘安の役で沈んだとされる元寇船が出土しています。私が所属する宇宙地球環境研究所年代測定研究部では、引き揚げられた碇や木片などの遺物の年代測定を行なっており、もともと歴史に興味があった私は、この研究に参加することになりました。
遺物の中でも鉄製のものは、海底堆積物中で腐食して原型を留めない塊になっています。鉄製遺物が海底でどのように腐食するのか明らかにすることで、鉄製遺物の元の形の復元や保存方法の検討に役立つと考えています。昨年秋には長崎県の鷹島にある水中遺跡で試料採取を行いました。船の上からダイバーの方が試料を採取するのを待ちながら、試料が無事に採取できるかという不安半分、鎌倉時代の遺物に出会えるというワクワク半分でした (写真1)。最終的にいくつかの木片と腐食した鉄製遺物、さらには遺跡周囲の堆積物コア(写真2)を採取することができました。調査には水中考古学や文化財保存など様々な分野の専門家が参加しており、引き揚げられた遺物の保存処理や元寇の歴史についても話を聞くことができました。現在は、分割した堆積物コアから篩とピンセットを使って貝殻や木片を分ける作業を地道に行なっています。堆積物からどんな情報が得られるか、とても楽しみにしています。
研究外の活動にも積極的に取り組む機会があります。例えば、年代測定研究部では毎年、小学生向けのイベントを開催しており、私も引率補助として参加しました。この活動は、苦労して取得した教員免許が役立つ機会になっています。その他にも、地球惑星科学科のイベントである学外セミナーの運営委員を務めたり、他大学が主催する研修に参加したりしています。
最近の研究外の活動の中で特に印象的だったのは、福島県での放射線測定研修です。大阪大学が主催し、学生が福島の浜通り地域に1週間滞在して土壌の線量測定や廃炉作業の現場を見学するという研修でした。学会が近く忙しい時期ではあったものの、原発事故のあった土地を直接見る機会はなかなかないと思い、参加を決めました。福島第一原発の見学では、線量計を持ち込みました。原子炉建屋に近づいたとき、線量計のアラームが鳴りました。飯舘村での研修を通じて、外の空間線量は十分安全なレベルになっていることを理解していましたが、事故が起こった現場を目の当たりにすると、恐怖を感じました。実習では、飯舘村の農地や森の中で土壌を採取し、放射能濃度とセシウム濃度の測定を行いました(写真3)。また、現地の方々の話を聞き、他の学生参加者と議論を重ねる中で、空間線量や土壌中のセシウム濃度が0になったら復興と呼べるのか、どのようにすれば復興を支援できるのか、といった問いについて考えました。専門や出身地が異なる学生との議論はとても刺激的でした。同時に、実際に現地に赴くことで、事故の影響を前にして福島の人々と自分がどう感じるかを知りました。そして環境の分析が社会に対してどのように貢献できるかを考える貴重な機会となりました。
大学院での生活は、新たな出会いとの連続ですが、私の場合、特にその出会いの回数や幅が多いかもしれません。その理由の一つは、炭素同位体の分析は炭素を含む多様な試料を対象にするため、異分野との接点が多いことです。もう一つは私が少しでも気になったら試さずにはいられない性格だからかもしれません。新しい知識や人、経験に触れるたびに、研究内容について深く考える時間が増えると感じます。新たな出会いにすぐ接することができる環境にいられるのは、とても幸運なことだと思います。

写真1: ダイバーによる鷹島水中遺跡調査中の海上のようす

写真2: 鷹島水中遺跡から引き上げられたばかりの堆積物コア

写真3: 放射線測定研修で土壌と植物の試料を採取するために他大生と飯舘村の山の中を歩くようす