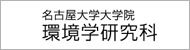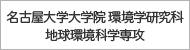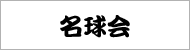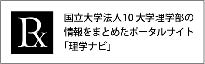新着情報
「地球環境科学と私」第五十三回
2025.4.17
「地球環境科学と私」第五十三回は大気水圏科学講座 相木 秀則さんによる 潮の声に耳を澄ます:海と人をつなぐ科学 です.
潮の声に耳を澄ます:海と人をつなぐ科学 大気水圏科学講座 相木 秀則
日本は四方が海に囲まれた島国であり、人々は古くから海と共に暮らしてきました。海の生物の営みや人々の生活、地域の風土に触れるなかで、太陽・地球システムが海をどのように動かし、潮の満ち引きがどのような環境をもたらしているのかを体感できる機会に恵まれてきました。自然災害の多い日本では、地学(地球科学)は物理・化学・生物と並ぶ理科4科目、あるいは理学4学科の一つとして位置づけられています。一方で、諸外国では、物理・化学・生物といった基礎的な学問領域を修めた後に、総合科学の一分野として地学(地球科学)や海洋科学へと進む教育体系が一般的です。海というフィールドの広さに呼応するように、海洋科学では分野を超えて多くの人が集い、環境問題からエネルギー開発、産業応用にいたるまで、多岐にわたる課題に向き合っています(写真1)。
私たちが知っている海は、実はほんの一部にすぎません。その未知の広がりは、海洋リテラシーの基本的な考え方としても位置づけられています。海は、人々に驚きや感動をもたらすと同時に、その奥深い科学的側面に気づかせてくれる存在でもあります。海は宇宙と同様に人類にとって未踏の領域であり、万物の神秘に対する畏敬の念を抱かせます。しかしながら、こうした「畏れ」や「尊敬」といった感覚を直接体験する機会は次第に減少しつつあり、それをいかに育んでいくかが今後の重要な課題となっています。知識の習得にとどまらず、単に自然の力を恐れるのではなく、それと共生する姿勢の重要性が2024年12月に名古屋大学フューチャー・アース研究センターが主催した公開シンポジウム「No Ocean, No Life」において示唆されました。人材育成においてもこの視点を取り入れることが、日本社会の発展に寄与するのではないかという意見が交わされました。
海洋の研究をする際には、その意義が社会との関わりのなかで定まってくることも少なくありません。ここで、私自身の関心も交えながら、愛知県と三重県に囲まれた伊勢・三河湾の歴史を少し振り返ってみたいと思います。1616年に東海道唯一の海路「七里の渡し」が始まりました。これは熱田神宮の前から三重県の桑名市(以下、現在の市名)まで船で渡るものです。当時は伊勢・三河湾で漁業が発達しており江戸時代から桑名は蛤の産地として有名でした。一方、知多半島においては半田市で1804年にミツカンの蔵元が酢づくりを開始して江戸までの海運がありました。1892年には三重県の鳥羽市で真珠の養殖が始まりました。また1903年には名古屋市中川区に下之一色漁業組合ができました。1912年ごろには木曽三川でヨハネス・デレーケによる河川改修が行われました。1959年に伊勢湾台風が来た後には名古屋港に防潮堤などができたために、下之一色漁港は衰退しました。伊勢湾は今でも土木工学の分野で高潮のモデル研究がよく行われる場所であります。伊勢湾台風によってもう一つ、愛知県西尾市の一色町では水田が水に浸かって、鰻の養殖に産業が変わっていき、1963年には矢作川からのうなぎ専用水道が設置されました。1988年には蒲郡市でアメリカズカップ(国際ヨットレース)の練習が開始しました。一方で、名古屋市港区の庄内川の河口には藤前干潟というところがあります。この保存活動が名古屋大学の寺井久慈さんなどの協力によってなされ、2002年にラムサール条約に登録されました。この庄内川と上流の土岐川では2003年からアダプトプログラムが実施されています。「アダプト」という言葉には“養子縁組”という意味があり、親しみを込めて場所を引き受ける感覚が込められています。たとえば、スポーツ活動で慣れ親しんだ河川敷を、自分たちの場所として清掃するボランティア活動もその一つです。このように地域に根差した新たな文化が育まれています。一方で中部国際空港ができたことなどにより2005年には常滑市にあった一連の大学のヨット部の施設が蒲郡市に移動しました。2010年には名古屋議定書、生物の多様性に関する条約、COP10がありました。2016年には伊勢志摩サミットがありました。
伊勢・三河湾というのはこのような場所であり、名古屋大学の教育活動にも、地域に根ざした歴史や環境との関わりが息づいています。そのうえで、地球規模の環境問題にも目をむけ、実際に海と関わる体験(写真2)と、そこから広がる学びの両方を大切にすることが、これからの社会にとっても大事なのではないかと感じています。

写真1: 海上の風が海洋浮遊ゴミをどのように動かすのかを学ぶための回転水槽実験のようす

写真2: 海上観測塔にて潮風に耳を澄ませて作業している筆者